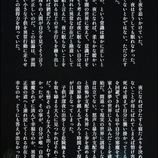夜目遠目夢の内
私は、もう、ずっと夜を追いかけていた。
体質なのだろうか、夜はどうしても眠れなかった。眠りたいとか眠りたくないとかではない。ただひたすら眠らなかっただけだ。
夜になれば眠るもの、という常識は確かに正しいと思う。普通なら誰もが、夜になれば、柔らかな暖かい布にくるまり、一面を闇の世界に変えて、意識だけを別の世界に飛ばす。そう考えれば夜に眠らない自分は、普通の人間の枠から外れた異常な存在だと勘違いしてしまうのは当然の帰結と言えた。夜に眠らないことを異常だと罵り、脳が揺れるほどの平手打ちを繰り出してくる母の事を考えれば猶更だろう。
自分は異常者だ。周りの人間が自分を見てそう言うのだからきっとそれが正しいのだ。この結論は、世間も世界も理解できない小さな子供を異常行動に走らせるのに十分すぎるほどの説得力を持っていた。
夜になればひたすら寝たふりを決め込んだ。寝ていないことが母にばれてしまえば情け容赦の無い暴力が死ぬ寸前まで自分に襲い掛かってくるが、運良くそれを回避できればもはや自分の邪魔をする者はいない。家人が夢の世界に入り込んだことを確認したら行動開始だ。間違って現実の世界に誘導しないように決して音は立てない。怒声と暴力が支配する世界から、未知と恐怖が支配する外界へと歩を進める。家人が現実への境界線を越えるであろう時間まで現実逃避に浸るのが日課となってしまった。
子供が深夜に出歩くなど危険極まりない。深夜徘徊を取り締まる大人に見つかればそれこそ一巻の終わりだ。生憎そのような大人と出くわすようなことは無かったが、その事が、自分が唯一自由になれる時間を邪魔されずに済んで幸福なのか、異常者である自分を正義の道へと連れ戻してくれる存在と出会えなくて不幸なのか、どうにも答えが出なかった。
そんな馬鹿げた浅い反抗を繰り返していた時だった。
目の前に現れたのは、少なくとも世界のルールに違反する犯罪者を取り締まる正義の大人ではなかった。ただ目の前の人間らしきものがどうにも自分と同じ子供とは思えなかった。少なくとも自分と同年代、あるいはそれ以上なのだろうが、ただそれにしては人間であるという確証が持てない程にただただ美しかった。こういうのを神秘的、と呼べばいいのだろうか。
こんな夜更けに散歩でもしているのか。言葉が出ずに立ち尽くしていると、簡単な挨拶と共にそのような事を言われた。そのようなところだ、と自分は答えた。確かに自分がしているのは夜の散歩だ。普通の人間が寝静まる時間を見計らっての深夜徘徊を散歩と呼称していいのであれば。
目の前の人は言った。自分も似たようなものだ。今日に限ってなぜか眠れないから、散歩でもしてみようと思ったのだ。事情は違えども、どうやら目の前の人は自分の同類であるらしい。まさかこんなところで仲間に出会えるとは思っていなかった。
立ち話に興じてもよかったが、この場で暢気にしていれば、いつ望まぬ正義が平和の鉄槌を振りかざしてくるやら分かったものではない。目の前の人の案内の元、人目につかない場所に移ることとなった。
それからというもの、互いの素性を知らぬまま取り留めのない話が続いた。先の未来の事を一切考えない、ただの雑談。浮かぶ星が綺麗だとか、花の匂いがたまにきつい事があるとか、夏は暑いとか、冬は寒いとか。出会ってから何時間も無意味な会話を繰り広げ、気が付けば家に戻る時間が近づいていた。
もう帰らなければ。そう告げて立ち去ろうとした。その人はそんな自分に待つように促した。帰らなければ親に怒られる。その人と話せなくなるのは惜しいが、親に怒られたその結末を想像するとさすがに恐怖の方が勝った。最後に一言だけ。その人はそう懇願してきた。ほんの1分ほどでいいのだ。現実的な提案がやってきた。そうなれば根負けするしかなかった。
あなたは夢を見るか。取り留めのない話とは違う、それは問いかけだった。
子供には夢を見る時間が必要だ。その人の声が奇妙なまでに頭に響く。
寝て見る夢でこそ、得られるものがあるのだ。言葉が頭の中で反響する。
次第に目の前が闇に支配されていく。その人の姿が輪郭を失っていく。頭を撫でられたのだろうか、その感触も怪しくなっていく。もはや最後の言葉は何だったか認識できない。
お休みなさい。その言葉を認識できた時には、自分は家の寝床に転がっていた。
生まれて初めて味わった睡魔は、それからの自分を変えてしまった。決まった時間になれば動けなくなるほどの眠気が襲ってくるようになった。体を横たえている間、誰かが近づく気配に気づけなくなった。暗闇の世界に入り込んだと思った瞬間には、眩しい光の世界に移されていた。
夜の世界を、出歩けなくなってしまった。
周囲の人間どもはこの変化を喜んだようだが、自分は逆に絶望に打ちひしがれた。眠らない世界を歩き回るあの感覚を二度と味わえないのだ。唯一自由になれる時間を奪われたのだ。心から平和を噛みしめることのできるひと時が消え失せてしまったのだ。
そして何よりも、あの人にはもう会えないという事実が、ただひたすら悲しかった。
あの美しい人ともう一度会いたかった。誰もが眠りにつく闇の世界でこそあの人に会えたのだ。光の世界では絶対に会えないという奇妙な確信があった。ろくに別れの言葉も言えないまま自然と引き離された、その事実を上書きしたかった。夜に眠れるようになった、正常な人間になった、その喜びを噛みしめさせられる事に耐えられなかった。
孤独な世界に、ようやく見つけた仲間。
異常だからこそ、出会えた友達。
また、会いたかった。
それから不毛な努力が続いた。あの人に会うためにいかにして眠らずに済むか、あらゆる対策を試した。だがそのいずれも無駄に終わった。だが何年かかろうと、もう一度会えるなら、いくらでも求めよう。
たった一度の幸せを取り戻すために、今も眠らない夜を追いかけている。