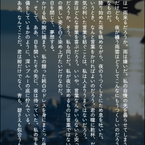DRESS
私は、もう、ずっと夜を追いかけていた。
夜というやつはまったく、逃げ足が早くてかなわない。私が全力で追いかけても、同じ速度で逃げていく。早すぎも、遅すぎもしない。まるで私が追いかけてくるのを愉しんでいるように、もしくは、追いついてくるのを待っているかのように。そんな挑発的な態度の夜に対し、私のほうもすっかりむきになってしまって、今日も私は夜を追いかけることに全力を傾けていた。
さて、私の追いかける夜というものは、とてもうつくしいものであった。昨日は宝石を散りばめた紺の天鵞絨のドレスを纏っていたが、今日は灰と黒を混ぜ合わせた着物を着ていた。軽やかな足取りで私の手をすり抜けて逃げていく夜は、なんと妖しく、神々しさに満ちていることだろう。そして、そのたび思うのだ。私なら、夜にもっとよく似合う白いドレスを着せてやれるのに、と。
夜の着物の裾の方で、灰色がゆらゆらとゆらめいている。これは一雨来るだろうか。雨は嫌いだ。私の自慢の光を曇らせてしまうから。だけども、夜が纏う雨雲はどうしてこんなにもうつくしいのだろう。不思議なものだ。私は降り始めた雨を眺めながら、夜のうつくしさにため息を吐いた。こういうとき、なんと言葉をかければよいのだろう。君の瞳に乾杯、だとか、気の利いた言葉を紡ぐことは、私は人よりうまくはないだろう。夜。君はどんな言葉を喜ぶだろう。いいや、言葉なんかいらないと突っぱねるだろうか。そう、私も同じだ。私が夜に求めるものは言葉ではない。ただその美しい姿を白く染め上げたいだけなのだ。
私は目を閉じて、夢想する。追いかける私の腕に捕まり、私の贈った純白のドレスを身にまとった夜の姿を。そして、ああ、目を開いたその先に、夜は待っていた。私の手を取る準備をしているかのように、深いブルーの底に佇んでいる。
夜、ああ、なんてことだ。君は紺だけでなく、青も、碧さえも似合うんだね。君に着こなせない色なんかないんだろうな。それならきっと、明るいオレンジも、豪奢な金色もよく似合うだろう。でも、やはり君にはこの色がいい。だからこの手を取って、着てくれるかい。僕の贈る、白のドレスを。
夜は頷いたように見えた。それだけで、私はどこまでも駆けていけるような気になった。
私が夜の手を取り、夜が私の手を取った。
「今日は白夜だね」
「不思議だなあ。白夜って、どうして夜が来ないんだい?」
「ああ、それはきっと、夜が昼のやつに捕まって、昼色のドレスを着せられちまってるのさ」
遠く遠く、はるか遠くから、風を渡る誰かの声が聞こえた。